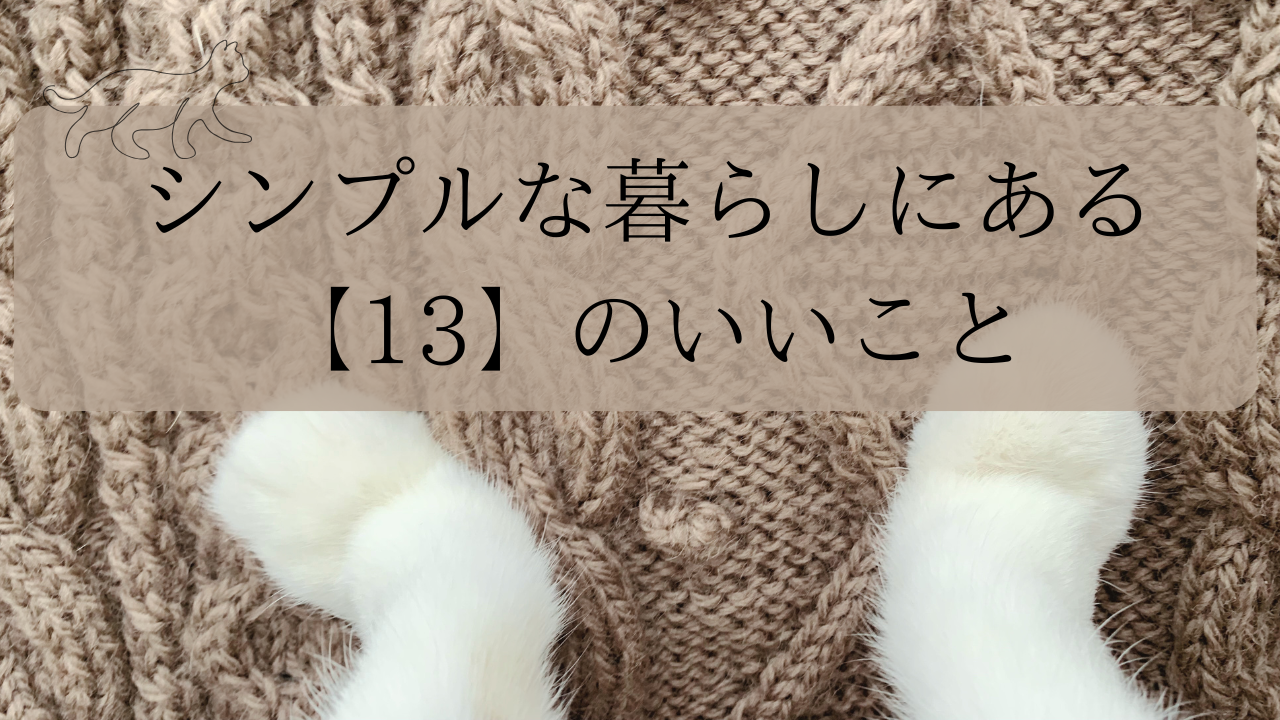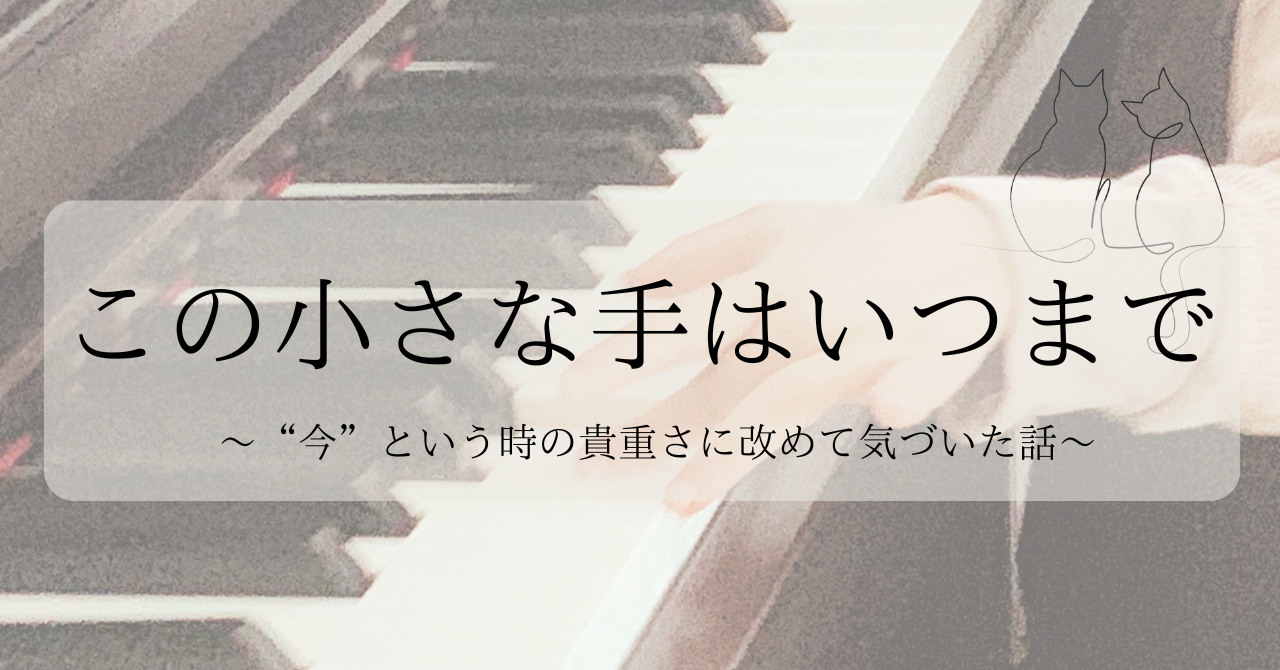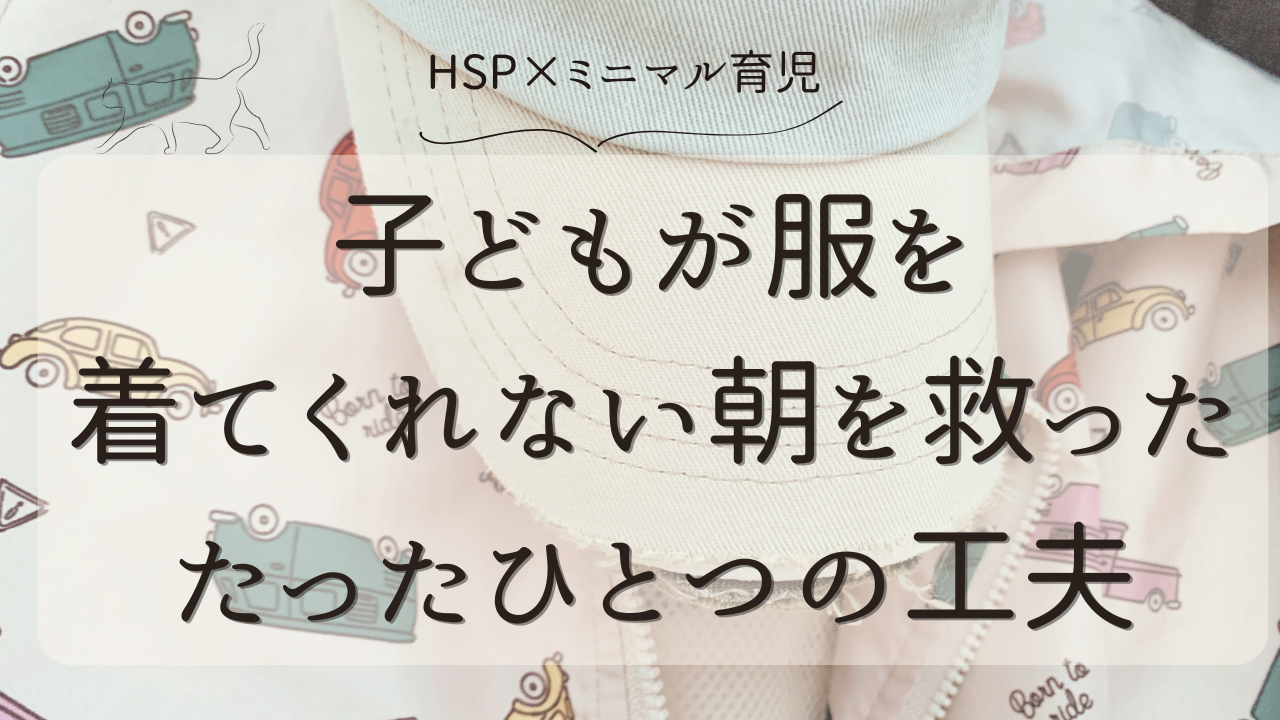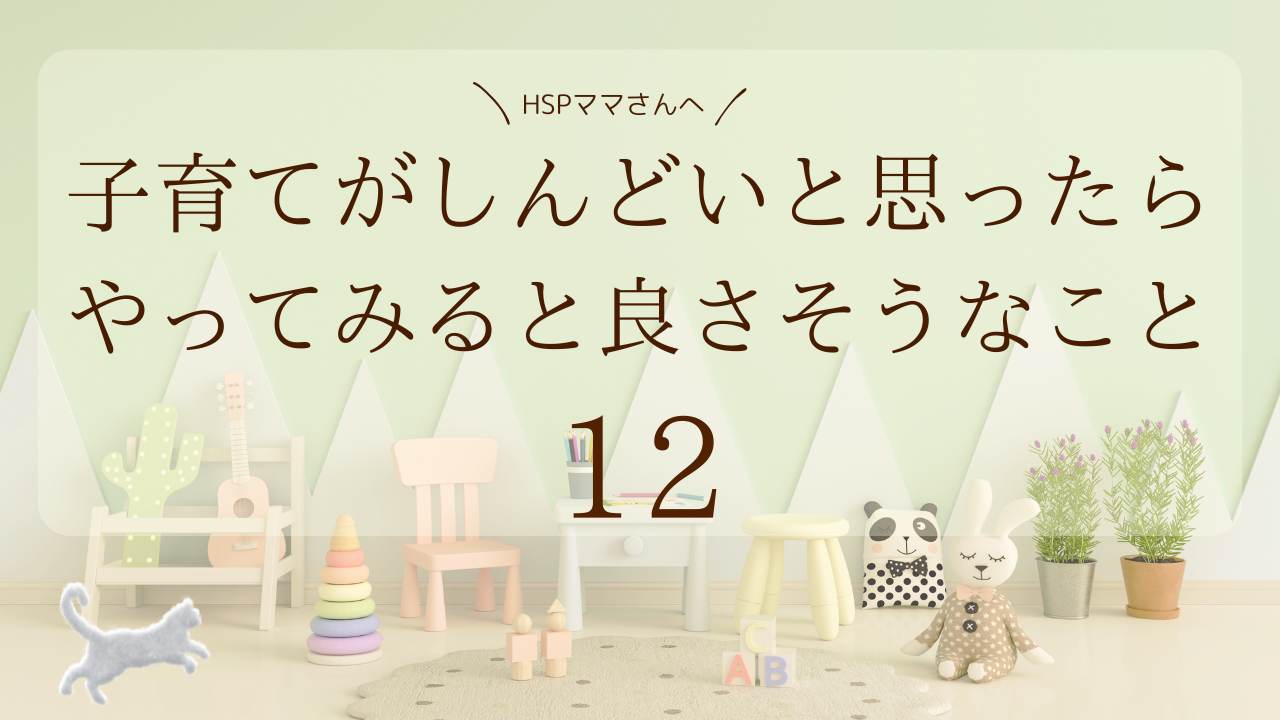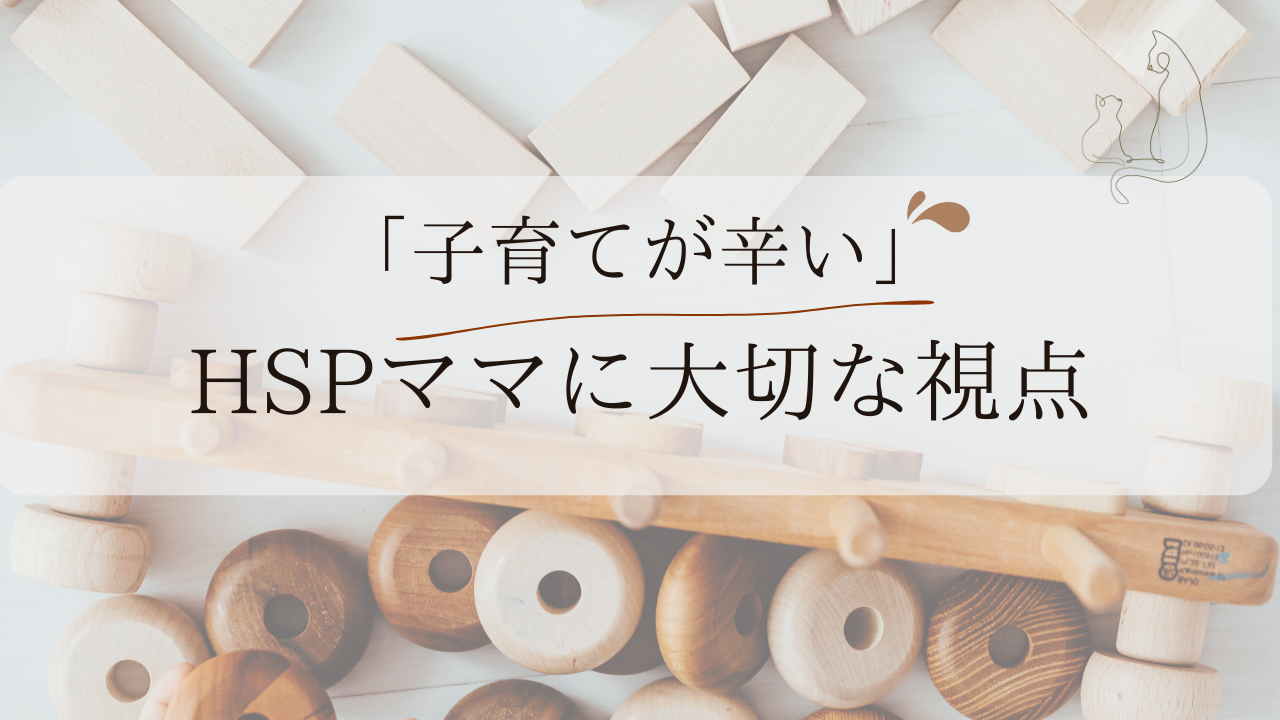【つい怒っちゃう】子育てを楽にするために〈怒る〉について考える
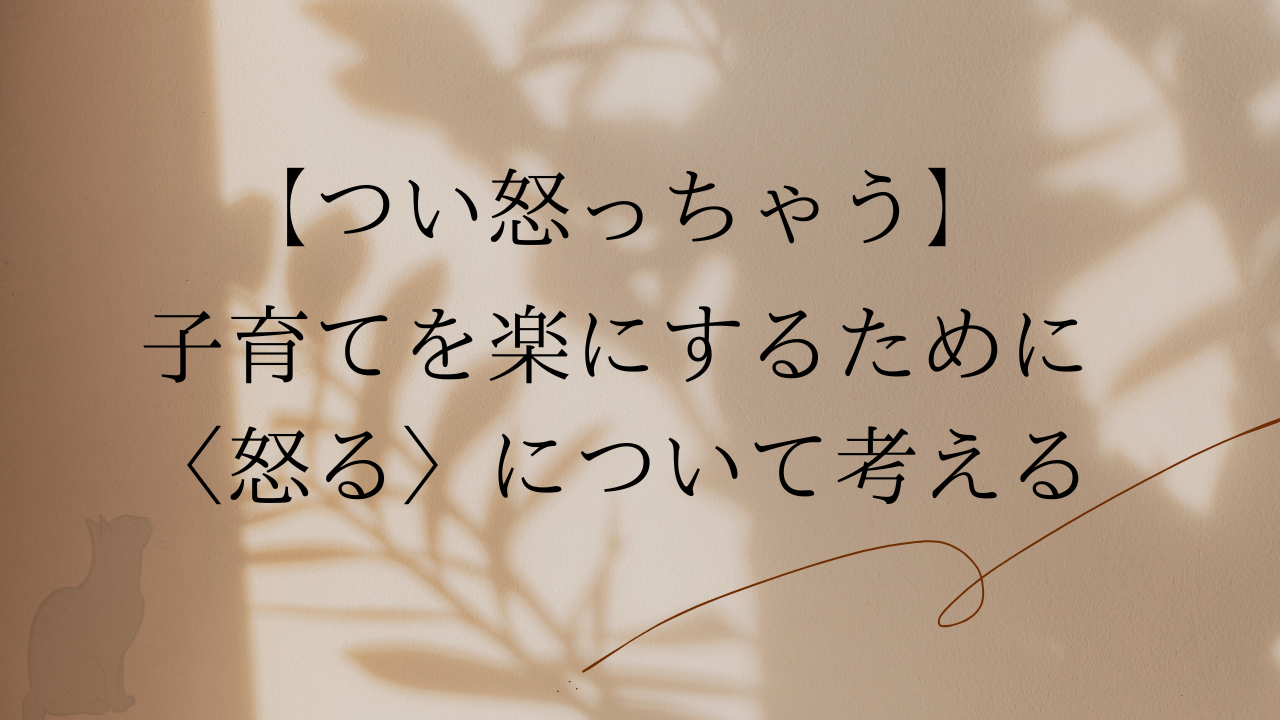
こんにちは、mikiです。
皆さんは、怒ることがありますか?
先日、息子のこつんを幼稚園に送った帰り道、ふと「怒る」ということについて考えていました。
なぜ、私は怒るのだろう。
怒るって無駄だよな。
子どもに対して寛容になれない自分を情けなく思うこともあります。
そこで、「怒る」ということについて考え、自分自身が楽になる方法を考えてみたいと思います。
「怒る」とは

「怒る」は演技?

ついつい怒っちゃうことは、きっと誰にでもあるよね。。
毎日毎日子育てお疲れさま。
毎日繰り返される子どものめちゃくちゃな言動に感情をコントロールできず、つい怒ってしまうことがあります。
でも、冷静に考えると、全然怒る必要がなかったり、あるいは、怒るという演技をしているのではないかと思うことがあるのです。
すごく怒りに満ちていた気がするけど、近くを通りかかったご近所さんに「あ、こんにちは」と声色を変えて挨拶できることはないでしょうか。
こういう時、「あ、今の怒りは演技だ」と我にかえるのです。
つまり、怒りはコントロールできるはずなのではと思うわけです。
「怒る」は無駄が多い
怒ること、イライラすることは無駄が多いなと思います。
怒ることは、他の感情と比べても圧倒的に疲れます。
怒ると、疲れる
怒ると、エネルギーを消費する
怒ると、時間がかかる。
怒ると、怒ったあともしばらくイライラとしている
怒ると、シワが増える
怒ると、ストレスが溜まる
一方で、怒ることで得られるメリットは全然ないことに気付かされます。
子どもに対して感情的に怒ったところで、子どもの発達にいいことがあるでしょうか。
もしかしたら、その時、その場面では、親の怒りに対して恐怖心を抱き、その結果、親の言うことを聞くかもしれません。
でも、長期的に見ると、それにメリットはなくて、「自分は親を怒らせてしまう存在」と自己肯定感が下がったり「怒られたからやめた」という他人軸の理由で行動したりすることになります。
本来、自分軸で行動できることが望ましいはずです。
これをすると、相手が喜んでくれて自分も嬉しくなる。
あれをすると、相手が悲しんで自分も悲しくなる。
こういう経験を積んでいくことで、徐々に行動の善悪を学んでいくのだと思うのです。
「怒る」ことは何も生まず、ただただ消費する行為であると、心に留めておきたいところです。
なぜ怒るのか
なぜ子どもに対して、怒ったり、イライラしたりするのでしょうか。
それはきっと、自分の思い通りにならないからではないかと思います。
あと5分で家を出ないといけないのに、遊び出す。
動画視聴の終わりの時間を過ぎているのに、なかなかやめない。
もう寝る時間なのに、騒ぎ出す。
などなど
これらの事に対して、子どもと一緒に決まりを考えていたとしたら、どうでしょうか。
決まりを守れなかった事に対して、「叱る」必要はありますが、「怒る」必要はありません。
この場合は、冷静に話が出来るはずです。
でも、ここでもし、怒りの感情が出てきたとしたら、それはなぜなのでしょう。
きっと、自分の中で、「決まりは絶対に守らなければいけないもの」という確固とした思いがあって、それに反する行為であるからではないでしょうか。
そう、「自分の思い」に反するから怒りが湧き起こってくる気がするのです。
同じ決まり事の中で、同じ子どもの行為を見たとしても、怒る人とそうでない人がいるのは、この「自分の思い」の違いにあるのかもしれません。

思い通りにいかないのが普通なんだけどね。
毎日のことだと、忘れがち・・・。
「怒る」をコントロールする

長期的に考える
一つ目の方法として、長期的に考えるということをあげたいと思います。
私たち親がしていることは、子どもを育てることです。
子どもが、幸せに、自分の力で生きていけるように、土台づくりをサポートしているに過ぎません。
子どもが本来もっている能力を伸ばせるように、サポートしているだけ。
子はいずれ親の元を巣立っていくのです。
このゴール(門出?)を見据えて接するのと、そうでないのとでは、違いが出てくるように思います。
例えば、怒ってばかりいる親に育てられてた人と、大らかに見守ってもらって育てられた人とでは、自己肯定感や判断力などに違いがあると想像できます。
(論理的な根拠はありません。きっとそうじゃないかなと想像しているに過ぎません。)
自分に置き換えてみたら、よりわかりやすいかもしれません。
例えば、会社で上司に毎日毎日怒られていたら、仕事に対するやる気も自分に対する自信も失われていくような気がします。
逆に、失敗しても怒らず、その原因を一緒に考えてくれたり、頑張っている姿を認めてもらえたりしたら嬉しくならないでしょうか。
幼い子どもにとっては、家庭が人生の大半を占めています。
今、ここで「怒る」ことは、子どもの人生にどんな影響があるかを考えると、その必要性のなさに気づくことができるかもしれません。
そして、他の対処法が見つかる可能性があるのではないかと思います。
「怒らない」という実験
二つ目の方法は、「怒らない」実験をするということです。
いつからいつまで怒らないと決めて、それを実行してみるのです。
叱ることは必要ですが、怒ることは双方(親と子)にとってメリットはありません。
今日から3日間は怒らずに過ごすと決めて、それを守ります。
怒りそうになったら、それをメモしてみます。
いつ、どんな場面で、どうして怒りそうになったか、殴り書きでも、スマホにでもなんでもいいのでメモしておき、3日後に見返してみるのです。

何か気づきや、パターンが見えてくるかもしれないね。
その気づきを元に、解決策を考えていくのです。
解決策は、自分の中にあるかもしれないし、環境を変えることかもしれません。

ゲームのような感覚で実行していくと、それ自体が楽しくなっていくもしれないね。
言語化する
三つ目の方法は、怒ろうとしている寸前に、立ち止まって言語化するという方法です。
ちょっと難易度高めですが、怒らないと決めて過ごしてみると、意外とスムーズにできます。

自分が今からとろうとしていた行動を、頭の中で言語化してみるよ。
例えば、お風呂の時間になっても、一向にその気配を見せない時。
繰り返し伝えているのに全く行動しない。
いい加減イライラしてくる。また、声をかけなきゃ・・・。
この瞬間がチャンスです。
今、自分がやろうとしていたことを頭の中で言語化するのです。
今、大きな声を出そうとしていたな。
余計なことまで口から出そうだったな。
子どもの様子をしっかり見ていなかったな。(さっきよりも少し進んでるかも?)
ここで怒るとイライラを継続させるところだったな。
本当にあと1分でも3分でも待てないだろうか。
などなど。
あれこれ考えているうちに、「怒る」エネルギーがしぼんでいきます。
これができたらもう大丈夫。
「怒る」ではなく、「叱る」に切り替えられます。
「怒る」は何も生みません。
そう考えると、立ち止まって考えることに価値が出てくると思えます。
縛られず、おおらかに

我が家の飼い猫そうちゃんは、全然怒りません。
幼くて何もわかっていなかった1-2歳頃のこつんに叩かれても、尻尾を握られても、息をかけられても、何をされても全く怒りませんでした。今ももちろん怒りません。
そういう性格の優しい猫なんだなと思っていますが、このおおらかさは見習いたいものです。
子どもは、この世に生まれてまだほんの数年なのだから、社会のルールや物事の善悪なんてわからなくて当然。
命に関わることではない限り、「しつけ」という言葉に縛られずに、おおらかに接していきたいと改めて思うのです。
「叱る」は必要。でも「怒る」は必要ない。
怒りをコントロールしようと意識しながら過ごすだけで、穏やかな日々にまた一歩、近づける気がしています。
今日も穏やかな気持ちで過ごせますように。
最後まで読んでくださりありがとうございました。


.png)